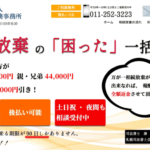家族信託と遺言書の違いを知らないと損する?相続対策の新常識を解説
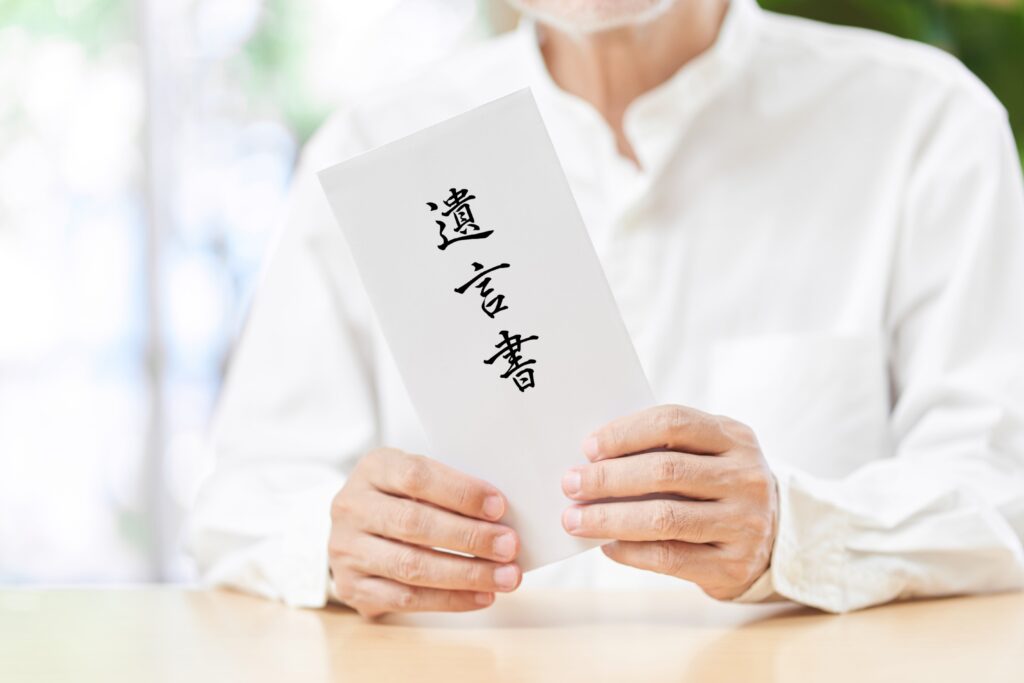
相続の準備と聞くと、多くの人がまず「遺言書」を思い浮かべます。しかし、近年注目を集めている「家族信託」は、財産管理や承継をより柔軟に行える新しい選択肢です。この記事では、家族信託と遺言書の根本的な違いやそれぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。ぜひご一読ください。
家族信託と遺言書の基本的な仕組みと目的の違い
家族信託と遺言書は、どちらも財産を「誰に・どのように」引き継ぐかを決めるための制度ですが、根本的な性質が異なります。まずはそれぞれの仕組みと目的を理解しておくことが重要です。
家族信託の基本構造とは
家族信託は、委託者が自分の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、受託者がその財産を管理・運用・処分する制度です。
たとえば、高齢者が将来判断力を失っても、受託者が代わりに財産を管理できる仕組みになっており、認知症対策としても注目されています。生前から意思を反映できる点が、家族信託の最大の特徴です。
遺言書の役割と限界
遺言書は、本人が亡くなった後にその内容が効力を発揮する「死後の指示書」です。相続人の指定や財産の分配方法を定めることで、相続トラブルを防ぐ役割をもちます。
しかし、遺言書はあくまで「死後」に効力が生じるため、本人が生きている間の財産管理や認知症による意思能力低下には対応できません。
目的の違いがもたらす活用シーンの差
家族信託は「生前の管理」にも使える制度であるのに対し、遺言書は「死後の承継」を目的としています。
つまり、家族信託は「今から未来まで」をカバーし、遺言書は「亡くなった後」のみを対象とする制度です。この違いを理解しておくことで、自分に最適な対策を選ぶ判断材料になります。
実際はどう違う?管理・運用・承継の仕組みを比較
制度の仕組みだけでなく、運用面での違いを把握することが、実践的な相続対策につながります。ここでは、家族信託と遺言書の実務的な違いを整理します。
財産の管理権限と活用の柔軟性
遺言書では、本人が亡くなるまで財産の管理権限は本人にあります。これに対し、家族信託は契約締結後から受託者が財産を管理できるため、判断力が低下してもスムーズな管理が可能です。
たとえば、アパート経営をしている人が認知症を発症しても、受託者が家賃管理や修繕契約を継続できる点が大きな違いです。
税金・費用面での実質的な違い
家族信託の契約時には登記や専門家報酬などの初期費用が発生します。一方、遺言書は自筆であれば費用を抑えられますが、公正証書遺言にする場合は手数料が必要です。
ただし、家族信託を活用すると遺言執行の手続きや遺産分割協議が不要になるため、結果的に手間やトラブルを減らすことができるケースもあります。
第三者との取引や手続きの実効性
遺言書は死後に相続登記や名義変更を行う必要がありますが、家族信託では生前から受託者が登記名義人となるため、手続きが簡略化される場合があります。
これにより、相続開始後の煩雑な手続きを避けられ、スムーズに資産を承継できる点が評価されています。
家族信託が注目される理由と遺言書との使い分け方
ここ数年、家族信託を検討する人が増えています。その背景には、社会の高齢化や認知症の増加、そして従来の遺言制度では対応しきれない課題があります。どのような場面で家族信託を選ぶべきかを理解しておきましょう。
認知症対策としての強み
遺言書では、本人が認知症になった後の財産管理には対応できません。判断能力を失うと預金の引き出しや不動産の売却も難しくなります。家族信託では、受託者がその役割を引き継ぐため、生活費の管理や介護費の支払いなどが滞る心配を減らせます。この点が、実務上大きな安心につながる理由です。
二次相続・孫への承継まで指定できる柔軟性
遺言書では「自分の死後に誰に渡すか」までしか指定できませんが、家族信託では「その後、誰に渡すか」まで段階的に承継先を設定できます。
たとえば、配偶者の死後に子ども、その後に孫へと財産を引き継ぐことが可能です。このような多段階の指定ができるのは、家族信託ならではの特徴です。
家族構成や財産内容に応じた使い分けが鍵
一方で、家族信託が万能というわけではありません。相続人間の公平性を重視したい場合や相続税の配慮を細かく記載したい場合は、遺言書の方が有効なケースもあります。
したがって、家族信託と遺言書を「併用」することが最も現実的な解決策といえるでしょう。遺言書で法的な遺産分割の指定を行い、家族信託で生前の管理を補完する形が理想的です。
まとめ
家族信託と遺言書は、どちらも大切な相続対策の手段ですが、その目的とタイミングが異なります。遺言書は死後の意思を形にする制度であり、家族信託は生前から財産を託して管理できる仕組みです。とくに、認知症や高齢化による判断力の低下が懸念される現代社会では、家族信託を活用することで「生きているうちから」安心を確保することができます。一方で、遺言書は法的拘束力が強く、相続人間のトラブル防止に有効です。両者の違いを正しく理解し、自分の家族構成や資産状況に合わせて使い分けることが、無駄のない相続対策につながります。知らないまま放置すると損をすることもあるため、早めに専門家に相談して最適な備えを整えましょう。