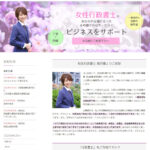親が認知症でも相続できる?成年後見制度の活用法
 親が認知症になると、財産管理や相続に関して多くの制約が生まれます。意思表示が難しくなることで、遺産分割協議や名義変更が進まなくなり、相続人同士のトラブルにつながるケースもあります。本記事では、親が認知症になった場合における相続の実務と、成年後見制度を使った対応方法を解説いたします。
親が認知症になると、財産管理や相続に関して多くの制約が生まれます。意思表示が難しくなることで、遺産分割協議や名義変更が進まなくなり、相続人同士のトラブルにつながるケースもあります。本記事では、親が認知症になった場合における相続の実務と、成年後見制度を使った対応方法を解説いたします。
認知症と相続手続きの関係とは
親が認知症になった場合、相続に関する多くの手続きで問題が生じます。そもそも遺産分割協議には、全相続人の「意思能力」が必要とされます。意思能力とは、自身の行動の意味や結果を理解し、判断できる力のことです。認知症が進行するとこの意思能力が失われ、法的な手続きに支障が出ることが少なくありません。
認知症の親が生存中で、その財産を売却するなどの処分を行いたい場合にも、同様の問題が発生します。たとえば不動産の名義人が認知症で意思表示ができない場合、その不動産を売却して介護資金に充てたいとしても、手続きが止まってしまいます。こうした状況を解消する手段として、成年後見制度の利用が重要になってきます。
意思能力の有無が手続きの成否を左右する
民法では、相続の手続きにおいても法律行為としての「合意」が必要とされており、それには全員の意思表示が求められます。認知症の親が「理解できない状態」である場合、たとえ家族間で同意が取れていても、手続き自体が無効になるリスクがあります。これは遺産分割協議書に署名・捺印する行為ひとつ取っても例外ではありません。
判断力が不十分な状態での署名は無効になる可能性も
親が軽度の認知症だったとしても、その時点での判断能力が明確でない場合、後日トラブルに発展することがあります。署名後に「このときは判断できていなかった」と他の相続人から異議が出ると、協議のやり直しや家庭裁判所での争いになる可能性もあります。
成年後見制度とは?仕組みと使い方
認知症によって意思表示が難しい場合でも、成年後見制度を使うことで法律上の手続きを代行できます。成年後見制度とは、本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が選任した後見人が代わりに財産管理や契約行為を行える制度です。
成年後見制度の主な特徴
成年後見制度は、家庭裁判所に申立てを行うことで開始されます。認知症と診断された親に代わり、子どもや第三者が後見人として選任されると、以後その後見人が財産の管理、遺産分割協議への参加、不動産の売却などを行えます。重要なのは、後見人の権限が明確に法的に定められている点です。
後見人ができること・できないこと
後見人は、本人に代わってあらゆる法律行為が可能になります。ただし、家庭裁判所の許可が必要な行為もあり、勝手に財産を処分したり、相続人の意向に反して手続きを進めたりすることはできません。本人の利益を最優先に考えながら行動する義務があるため、第三者によるチェック機能も整っています。
申立てから開始までにかかる期間
家庭裁判所への申立てから後見開始決定が下りるまでには、おおよそ1〜3か月程度かかります。診断書の準備や必要書類の提出、面談などが必要であるため、早めの対応が求められます。突然の相続が発生する前に、認知症の兆候が見られた段階で手続きを検討するのが現実的です。
相続における成年後見制度の実際の使い方
成年後見制度は、相続発生前後のそれぞれの段階で異なる役割を果たします。制度を使うタイミングや方法を誤ると、かえって手続きが複雑になることもあるため、正しい運用が求められます。
相続発生「前」に活用するケース
親がまだ存命中で、将来の相続を見据えた不動産の処分や資産の整理を行う場合、成年後見制度が有効です。たとえば、自宅を売却して老人ホームの入居費用に充てたい場合、本人に代わって後見人が不動産売却を進めることができます。その際には家庭裁判所の許可が必要ですが、法的なトラブルを避けながら財産管理を行えます。
相続発生「後」に活用するケース
親が亡くなった後、遺産分割協議が必要になりますが、認知症の親が遺産分割の当事者だった場合(たとえば共有名義の不動産があるケースなど)、成年後見人がその協議に参加する形になります。後見人はあくまで本人の法定代理人として行動するため、協議内容にも慎重さが求められます。
任意後見制度との違いも理解しておく
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあり、今回解説しているのは認知症発症後に使う「法定後見」です。一方で「任意後見」は、元気なうちに将来の後見人を自分で指定しておく制度です。認知症リスクを想定した事前準備として、任意後見契約を検討するのも選択肢のひとつです。
まとめ
親が認知症になった場合でも、成年後見制度を使えば相続に関する手続きを進めることは可能です。本人の判断能力が低下している場合には、法律行為が制限され、通常の相続手続きが行えなくなります。しかし、家庭裁判所を通じて後見人を選任し、制度に則って行動することで、トラブルを未然に防ぐことができます。相続は感情的な問題も含むため、法的な枠組みを活用しながら冷静に対応することが重要です。今後の相続に備える上でも、成年後見制度の正しい理解と早めの準備が安心につながります。