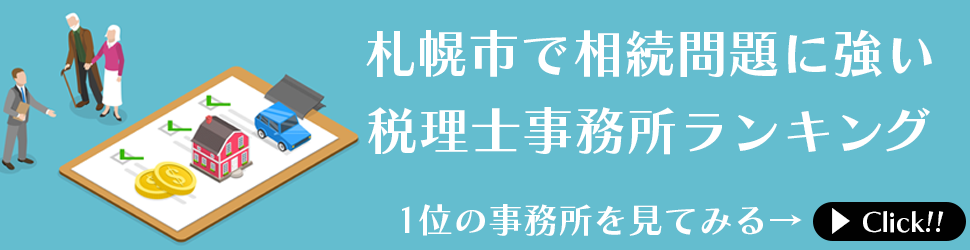土地?家?相続のときに課税対象となるものは?

相続が発生したとき、一番に心配になるのは相続税の問題です。「相続税は何にかかるのか?」「いくらかかるのだろう?」など悩みはつきません。相続自体、人生に何度も経験する事柄ではないため、わからないことだらけですよね。ここでは相続税に関して誰にでもわかりやすく解説します。相続問題が発生する前に事前知識として役立ててください。
そもそも相続税はどんなときにかかるのか
相続税とは亡くなった人が遺した財産を受け継ぐ際に課せられる税金です。財産が基礎控除額を超えた場合に支払わなければなりません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。
つまり相続人が1人の場合、3,600万円以下であれば基礎控除額の範囲内であるため、相続税はかからず、申告も不要です。
相続人が2人いると基礎控除額は「3,000万円+1,200万円」となり、4,200万円までが無税、これを超えた額を相続する際に相続税を支払います。
課税対象となるものは何か
相続税は土地・家屋・現金・預貯金・株券・生命保険・死亡退職金などプラスの財産から借金・貸付金・未収金・ローンなどマイナスの財産を引いた額が課税対象です。
書画骨董などは生前から鑑定に出し、資産価値を明確にしておくと、いざというとき相続税を支払う見込みが立ちます。
墓地・仏壇・神棚などは相続しても課税対象とはなりません。生命保険と死亡退職金は法定相続人の数×500万円までは非課税です。
税額から控除・軽減されるものとは
相続する財産の総額から控除・軽減されるものがあります。代表的なものが「配偶者控除」と呼ばれる税金軽減措置ですが、ほかにも数種類の控除や特例が認められているので、参考にしてください。
配偶者の税額軽減
亡くなった人の配偶者には1億6,000万円までの特例「配偶者控除」が設定されています。
この金額を超えた額を相続するにしても、法定相続分(相続割合1/2)以内であれば全額非課税となるので、実質配偶者の相続税は発生しないと考えてもいいでしょう。しかし配偶者控除を受けるためには、相続税の申告が必要です。
小規模宅地等の評価減の特例
自宅や商店、土地の相続において、評価額が高いと相続税が上がり、家屋を手放す事態に陥ります。
これを避けるため、宅地の相続には特例が設けられており、最大で80%近く評価額を減額できるのです。1億円の土地が2,000万円の評価額に下げられ、相続税の軽減になります。
未成年者控除
相続人が未成年者であると、相続税の控除が認められます。20歳になるまでの年数×10万円が控除額です。たとえば相続人が15歳だとすると、50万円の控除が受けられます。
障害者控除
障害のある方は85歳まで控除が受けられる障害者控除の制度を利用しましょう。年数に応じて1年に10万円が控除されます。
たとえば55歳で障害を持った方が相続人になると、85歳-55歳×10万円で300万円が控除される金額です。特別障害者は1年につき20万円となります。
相次相続控除
相次いで相続が発生することを相次相続と呼びます。10年以内に2回以上相続があった場合は、相次いで2度の相続税を支払わなければなりません。
こうした税負担軽減のために1回目の相続できちんと相続税を払っていれば、2回目の相続では税額の控除が受けられます。
贈与税額控除
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。相続時精算課税方式を選択した場合、2,500万円を超えた贈与には贈与税を支払わなければなりません。
相続時には既に贈与された財産と発生した相続財産を合算して、相続税を算出します。既に支払った贈与税との二重課税を防ぐために、贈与税額控除が設けられているようです。
損をしないためにも専門家に相談して早めに対策しよう
相続税に関する問題は身内で解決しようとせず、専門家に相談して、対策をとった方が賢明です。相続税は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告、納付しなければなりません。
納付日を過ぎると延滞税がかかり、2か月を過ぎると税率自体が高くなってしまい、大変な負担を強いられます。近親者が亡くなった時点で誰もが相続人となるわけですが、相続税に関して充分な知識を持っていないと、自分で納付までこぎつけられないのが現実です。
多少の知識を持っていたとしても、親が亡くなったあと、子がやらねばならない手続きはほかにも多く煩雑なため、相続問題に充分な対応ができません。
死亡届を提出し、年金や健康保険への届け出や葬儀の手配をしながら、故人の全戸籍を集めたり、すべての相続人を集めて相続会議をしたりなど、やるべきことは山積みです。
財産目録を用意したところで、財産価値を確定し、そこから相続人すべてにかかる相続税を正確に算出するのは至難の業です。
専門家に任せると費用はかかりますが、前項で挙げた控除制度などを熟知しているので、気付けば大きな節税につながります。相続税問題は早々に専門家に相談し、対策を立てましょう。
まとめ
相続税は受け継ぐ財産が基礎控除を上回る場合に発生します。土地、家屋、現金、預貯金などのほか、借金、ローンなども負の遺産として相続されるものです。
配偶者、未成年者、障害者には控除・減額される制度があることを覚えておきましょう。さまざまな控除制度がありますが、これらを上手に利用し節税するには、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。